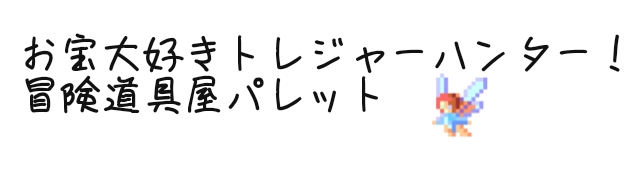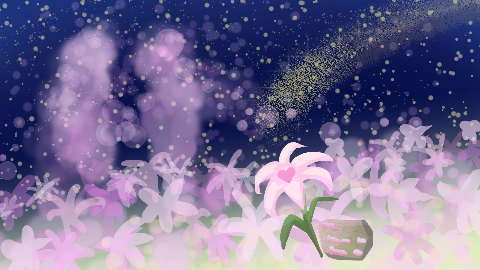『鋼の道しるべ』
参考文章量【長め:約6700字】

この島の資源の一つに、「魔石」と呼ばれる不思議な石がある。名の示す通り魔法の力を秘めたその石は、未知の部分が多く制御には専門的な技術を要するが、様々な奇跡を起こす源として重宝されている。
幾重にも積み重ねられ、失われてきた歴史の一つに、魔石の力で高度な文明を築いた時代があった。
当時の人々は長年の研究により魔石から魔力を抽出し機械を動かす動力として利用する技術、すなわち「魔導」を得ていたのだった。
人々はより便利で快適な生活を求めた。より純度が高く強大な魔力を持った魔石をめぐり、やがて人々は争うようになった。
魔導の力を行使しての戦いは熾烈を極め、長期に渡り島全体を戦火で包んだ。いつしか魔導大戦と呼ばれ、一つの時代となった。
長きに渡る戦いの時代、とある荒野に隠された地下施設。そこに二機の兵器が格納されていた。自らの判断で独立して戦闘する最新型の魔導人形。多くの破壊兵器を搭載し攻撃に特化した壱式と、機動性に優れ撹乱や陽動に適した弐式。二機のコンビネーションで大きな戦果を挙げる、筈だった。
幸か不幸か、この二機の兵器は戦場に投入されることはなく大戦は終結した。隠された施設は隠された存在のまま、時の流れに飲み込まれてしまったのだった。
開発直後の試運転以来だろうか。
気の遠くなるような時を越えて、再び壱式が起動した。胸部に組み込まれた大型魔石が機体中に魔導の力を供給し始めた。何者かが施設内に入り込み、起動操作をしたのだろう。
幾つかのエラーを出しながら、ようやく頭部のメインカメラが起動した。経年により中々映像が安定しないが、その何者かを映し出した。
不思議そうな表情で覗き込んでいるのは、額にゴーグルをした冒険者風の青年だった。
「どうなってんだあ、コレ。動くのかな?」
目的があって起動させたわけではないらしい。
壱式は即座に侵入者に対する対処フローを検索した。しかしエラーとバグの多発で先に進まず断念、
実戦投入される前に随分とポンコツになってしまったものだ。
やむを得ず直接のコミュニケーションを試みることにした。知りたいことは山ほどあるのだ。大戦はどうなったのだろうか。
「……私ハ、魔導戦闘兵器……壱式」
ノイズ混じりではあったが、スピーカーから発声することが出来た。途切れながらも何とか事情を説明した。
「おおー喋った、何か分かんないけどすごいぞ!」
目を輝かせて一人で大騒ぎ、なかなか話を聞いてくれない。
「私ハ、魔導戦闘兵器……」「すごいすごいっ!」
仕方なく何度も同じ説明を繰り返すことになった。
冒険者から現在の状況を聞き出したかったのだが、彼は魔導大戦それ自体を理解できなかったようだ。長い時の流れは、あれほどの大戦の事実さえ覆いつくし消し去ってしまったらしい。
大戦に参加できなかったばかりか、結末を知ることさえ叶わなかった。情報処理ソフトウェア上に湧きあがるこのノイズは、人間で言うところの無力感や虚無感にあたるのだろうか。
そのような感傷、眼前の侵入者には特に伝わってはいないようで、相変わらず興味深げにメインカメラを覗き込んでいる。
「ねえキミ、この遺跡にはどんなお宝があるか、知っていたら教えておくれよ」
最新鋭の戦闘兵器を格納していた秘密基地も、今では地下遺跡と成り果ててしまっていた。
「コノ施設にノコッテイルトシタラ、私ノヨウナ戦闘兵器カ……大型ノ魔石グライノモノダロウ」
もはや不必要な代物だ。好きに広い集めて持ち去られても不都合はない。
「おっきな魔石か、いいねえ。ちょうど強力な動力源を探していたんだ。船を丸ごと空に浮かせるぐらいのね」
彼はプロのトレジャーハンターだった。空を飛ぶ旅客船「飛行船」の開発を目指す商人の依頼で、燃料となるものを探し求めて来たのだった。
「いやあ、夢物語みたいな話なんだけどさ、これを本気で実現しようとしている人がいるんだよ。冒険者として一枚噛まないワケにはいかないよね」
話しながらも目は輝きで満ちている。
確かに壮大な計画だ。「自在に空を泳ぐ船」私の時代にもそのようなものはなかった。せいぜい短時間だけ宙を舞う魔導人形くらいのものだ。平和な時代だからこその発想なのだろう。少しだけ興味が湧いた。
「コノ下ノフロアニ魔石ノ保管庫ガ有ルハズダ。行ッテミルトイイ」案内してやりたいが、まだしばらく動けそうにない。駆動系の暖気運転にやたら時間がかかっている。
「ありがとう、さっそく行ってみるとするよ。他にもお宝があれば頂いちゃおうかな」
冒険者は特に気にする様子もなく、破損した昇降機のシャフトに飛び込むと下層に降りていった。
室内に静寂が戻った。ただ、かすかなモーター音だけが響いている。壱式は次々と吐き出されるエラーを強制的に削除しながら、自らの身の上に思いを巡らせた。
戦闘のために生み出された存在でありながら、なんの戦果も挙げないまま戦闘不能に陥ってしまった。
今の私の存在意義は…一体なんなのだろう。一体なんのために目覚めてしまったのか。高性能な人工知能をもってしても、その答えを導き出すことは叶わなかった。
ほどなくして、ゴーグルの冒険者が戻ってきた。何やら小脇に荷物を抱えている。
「いやあ、残念。下の方はすっかり崩れていて魔石も粉々、まいったね」
さほど残念がっているようでもなさそうだが、空いた手で特徴的なとがった耳を触りながらボヤいている。
「見つけたのはコレだけ。キミの友達かな?」
彼が差し出したものは、ラジコン戦車のような小さな自動耕作機。それは変わり果てた姿の弐式だった。
見慣れた相棒の頭部パーツに強引に取り付けられたキャタピラー式の小型ボディ。そこには「農耕一号」と書かれた情けないステッカーが貼られている。
さほど大きな魔石も内臓されていないためか、エネルギー切れで運転ランプも消灯している。
兵器を必要としない世となってから、無理矢理改造されたのだろうか。かつての私なら、今の彼の姿を見て「哀れだ」と感じただろう。落ちぶれたライバルの姿に優越感を覚えたかもしれない。しかし今の心境は違ったものだった。時代にあった姿で、新たに役目を与えられた彼が「羨ましい」とさえ思った。
「感謝スル。ソレハタシカニ……私ノ友人ダ」
壱式は軋む関節を動かし弐式を受け取ると、お互いの魔導ケーブルを接続した。壱式のエネルギーを分け与えられた弐式はキリキリとキャタピラーを動かし、「タネヲマキマス、タネヲマキマス」と人工音声を流し始めたのだった。
「こりゃあすごい!」
冒険者は感嘆の声をあげると弐式を拾い上げ
「よし、さっそく外に連れていって種を撒こう」
手を差し伸べてきた。
この好奇心旺盛な青年には、警戒心というものは無いのだろうか。
しかし壱式としても、弐式の使命を全うさせてやりたい。ためらいながらも、その手を掴むことにした。
「……ちょっと重すぎやしないかな、キミ」
小柄な冒険者一人では重装備の壱式を支えられるはずもなく、二人で何度も転倒しながらようやく施設の外にたどり着くことができた。
弐式もキャタピラーをキリキリ鳴らしながら、ノロノロとついてきている。
周囲は見渡す限り美しい大自然だった。戦火に焼かれた廃墟と荒野の時代は、大きな時の流れに浄化され消し去られていた。
「さあ好きなだけ種をまくんだ、農耕一号くん!」
「タネヲマキマス、タネヲマキマス……」
冒険者は当初の目的も忘れて大はしゃぎしている。
「…………」
やはりこの島に必要なものは、戦闘兵器などではなく耕作機で間違いないのだろう。
この世界で私に出来ることは、弐式にエネルギーを供給し役目を全うさせることだけだ。それを終えたら……私は自ら運転停止し、内臓されている大型魔石を彼に託すことにしよう。飛行船の動力源のために消えるのなら悪い気はしない。
そう、決意した時だった。
「……………っ!」
あれほど騒いでいた冒険者が、何故か急に押し黙ってしまった。何やら、ひきつった表情で空を見上げ固まっている。
ゆっくりと彼の視線の先にメインカメラを向ける。なかなかピントが合わずもどかしかったが、その正体を捉えることができた。
……それは翼竜だった。
かなりの速度、真っ直ぐこちらに向かってきている。施設への避難さえ間に合いそうにない。
立ち尽くしている間に、竜が舞い降りてきてしまった。尾まで含めたら10メートル程だろうか。全身が黒い鱗で覆われ、黒い煙が立ち上っている。かなり高温な体表を持つ個体のようだ。歯をガチガチと鳴らし、明らかに威嚇している。
「まいったね……こりゃあ、カーボンドラゴンだ。でっかいなあ」
冒険者は立ち尽くした姿勢のまま、やや緊張感に欠ける感想を述べた。
「ダイヤモンドドラゴンの亜種でね、爪先が触れただけで丸焦げにされちゃうよ。中堅程度の勇者じゃ逆立ちしても勝てっこないヤバい奴さ」
竜から視線を反らさないまま、絶望的な解説を続ける。
生産直後の全盛期ならともかく、今の壱式では瞬時に破壊されてしまうだろう。当然、生身の人間や非戦闘型となった弐式も助かる可能性は無い。
それでも、今の状況では交戦するほかないと判断した。
壱式はゆっくりとカーボンドラゴンの前に移動、右腕に搭載された大型機関銃を構える。
「私ガ相手ヲスル。弐式ヲツレテ施設内ニ退避シテクレ」
言い終わるより先に、彼は弐式を抱えて走り出していた。薄情かと思えるほど判断が早い。
彼が背を向けたことが引き金となったのか、巨竜は上体を起こし臨戦態勢に入った。
竜は咆哮と共に距離を詰め、黒煙を纏わせた爪を壱式に振り下ろす。対する壱式は構えを崩すことなく安全装置を解除、竜の眉間に標準を合わせた。
……カチリ。空しい音がした。
そして弾丸が発射されることは無かった。
不発に終わった機関銃は右腕部ごと引き裂かれ、ゴトリと重い音をたて地面に転がった。
続けざまに繰り出された尻尾の一撃により、壱式は後方の樹木に叩きつけられてしまった。
メインカメラに亀裂が入り、破損した右腕の断面は熱で溶解している。かなり手痛いダメージを受けてしまったが、幸い制御系に深刻なエラーは生じていない。戦闘は継続可能だ。
そしてやはり、経年劣化によって実弾系の兵器は使い物にならないらしい。当然といえば当然、迂闊だった。
戦況は決して好ましいものではなかったが、壱式の中にあるものは悲壮感ではなく、高揚感であった。
いま初めて、戦闘用魔導人形として生まれもった使命を全うしようとしている。半ば諦めていた機会を与えられたのだ。
何とか立ち上がり、再び竜と対峙した。
急いで使用できそうな武装を検索する。
「高出力魔導砲」圧縮した魔導エネルギーを左掌から射出する兵器、これしかない。しかし強固な鱗に包まれている竜に十分なダメージを与えるには、時間をかけて最大までエネルギーを溜める必要があるだろう。
当然、眼前の竜がそれほどの猶予を与えてくれる筈はない。勝ち筋が見えないまま、やむを得ずエネルギーの充填を開始した。
左掌をかざした無防備な体勢のまま、相手の攻撃をかわし続けるより他にない。
「たとえば、ここで僕が加勢したら少しは事態が好転するのかな」
いつの間にか冒険者が戻ってきていた。
額のゴーグルを目元に降ろし、二本の短剣を逆手に構えている。表情は窺えないが、その声はとても落ち着いていて恐怖や焦りを感じさせない。よほど腕に覚えがあるのだろうか。
声に反応し、竜の視線が冒険者の方に移された。
ここで彼が少しでも時間を稼いでくれれば、勝機が生まれるかもしれない。
「まあ、やるだけやってみようかな」
先手を取ったのは冒険者の方だった。
竜が腕を振り上げるより早い跳躍、真っ直ぐに竜の喉元めがけて斬りかかった。狙いは竜属の弱点とされる逆鱗だろう。迷いがなく素早い攻撃だった。
しかし、その刃が相手に届くことはなかった。
竜の両翼から放たれる強烈な熱風を真正面から受けてしまったのだ。
「……………っ!!」
小柄な冒険者は全身から黒煙を上げながら、遥か後方まで吹き飛んでいってしまった。戻ってくる様子はない。あっけない退場だった。
そして、竜の視線は再び壱式に戻された。
壱式の重量と分厚い装甲は熱風に耐えうる強度はあったが、高温の爪や牙による直接攻撃の前にはまったく無力なものであった。
次々と繰り出される竜の猛攻により鋼鉄の装甲は瞬く間に破壊され、ついには脚関節の変形により身動きも取れなくなってしまった。
跪いた姿勢のまま左手だけは竜に向け続ける。
まだ僅かにエネルギーが足りない。
……その時、ノイズ混じりの人工音声が聞こえてきた。
「テキノ陽動、ソシテ撹乱!オレノデバンダ!サア、カカッテコイヨ、マヌケー!」
弐式だった。炭素竜の足元をノロノロと駆け回りながら、勇敢に声を上げ挑発をしている。
強引な改造で人型を失った弐式の姿は、敵として認識されなかったのだろうか。竜は賑やかに走り回る弐式を目で追いながらも、攻撃を加える様子は無い。
千載一遇の好機、エネルギー充填は完了した。
やはり私の相棒は頼りになる奴だ。足元の弐式に当たらぬよう、細心の注意を払いながら……渾身の一撃を放った。
………………………………………
………………………………
………………………
「いやあ、ひどい目にあったね。大丈夫だった?」
ようやく、吹き飛ばされた冒険者が戻ってきた。
衣服は所々焼け焦げ、いくつか擦り傷も見えるが大したことはなさそうだ。壱式は彼に変形した関節等を叩き矯正してもらい、何とか歩き回れるようになった。
結局のところ、壱式の放った魔導砲は竜の爪先を多少割った程度で、全くダメージを与えることは出来なかった。砲撃に伴う轟音と閃光に驚いて飛び去っていったに過ぎない。しかし、とりあえずの危機は脱することができたようだ。弐式も無事だ。
壱式は完全に戦闘不能となってしまったが、心から安堵するとともに達成感に満たされていた。思い残すことは、もう何もない。
壱式は冒険者に大型魔石の譲渡を申し出た。
「え、いらないよ。あぶないし」
あっさり断られてしまった。
彼が言うには、竜や怪鳥など一部の魔物は魔石を集めたりする習性があるらしい。今回の炭素竜も、壱式の持つ大型魔石に引き寄せられのかもしれないとの事だった。
「そんなの空飛ぶ船に積んだら大変なことになるかもね」
確かにその通りだ。あの竜に限らず、空中で魔物に襲われたらひとたまりもないだろう。
彼は大きい魔石は懲り懲りだと笑いながら、散らばった竜の爪先を広い集めて鞄に詰め込んだ。
この爪は、ごく少量でも大きな熱量を持つ燃料として価値があるらしい。これを飛行船の燃料として納品するのだという。
そして爪のお代だと言って、種の詰まった袋を差し出してきた。
「それはね、結界草の種。この草の周辺は誰にも探知できなくなるのさ。たくさん植えれば、もう人もドラゴンも入って来ないよ」もちろん僕もね、と笑う。
冒険者は種の育て方などを一通り説明すると、手を振りながら立ち去っていった。もう二度と再開することは無いだろう。
…………………………
……………
「モウ……ヘトヘトダ、補給タノム」
普段より更にノロノロ走行となった弐式を追いかけ魔導ケーブルを繋ぐ。
あれから、弐式は毎日せっせと結界草を育て、壱式は弐式の世話をする日々を送っている。
まだ花は咲かないが、魔物も動物も寄ってこない。静かな毎日だ。
当初、冒険者の提案には抵抗があった。多くの武器を搭載し戦闘兵器として生まれた存在でありながら、草花を育て平穏に暮らすなど考えられなかったのだ。彼には、そんな主張は一笑に付されてしまったが。
「僕だって冒険者として生まれたから冒険者やってるワケじゃないよ。やりたいことを勝手にやってんのさ」
戦うのも全然得意じゃないしね、と笑う。
「生まれもった素質とか才能を活かすのは素敵なことだけどさ。それに囚われて思うように生きられないなら、それってただの足枷じゃない?キミは本当に戦うことが好きなのかな?」
とてもそうは見えない、とでも言いたげだった。
自らの存在意義を否定されたようで、当時は多少の反感も覚えたのだが、結局は今の暮らしに落ち着いてしまった。
取り外せない武装が幾つか無駄に重たいが、行使することのない機能の存在も次第に許せるようになってきた。
「アナニハマッタ、タスケテクレー」
わりと忙しく充実しているのだ、この日々も。
「カメラニ虫ガクッツイテ前ガ見エナイー」
「ヨシワカッタ、マカセロ」
奮闘する二体の頭上には、雲ひとつない青空。
一隻の大きな飛行船がゆっくりと進んでいた。
完
![]() 待ってたよ☆
待ってたよ☆![]()
![]()
![]()
![]() よろしくね☆
よろしくね☆![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]() 何なら出演しておくれよ
何なら出演しておくれよ![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()